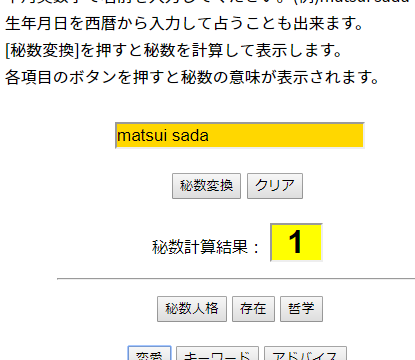文字には字源と呼ばれる起源があり、これを基に算出した字画に文字本来の意味が存在するとされています。
語源の字画で姓名判断する
姓名判断の原典を作り上げた熊崎健翁氏によると、名前の字画は途中で変化することなく、正しい字の源に基づいて、あくまで語源(旧制の漢字)の字画によるべきだと定義されています。
姓名判断ではその字画を利用するため、現在、私達が日常使っている略漢字と呼ばれる漢字の字画と、当サイトの姓名判断プログラムで示される字画が異なる場合が多くあります。
略漢字(新字体、新漢字とも言う)は元の漢字を簡単にする為に解かりやすく省略したものや、誤字が元になっている場合が多く、これらは漢和辞典に説明があります。
例えば、栄は榮で14画、会は會で13画で計算します。同様に、國→国、圓→円、なども字画が異なります。
名前の字画は日ごろ教えられてきた字画とは違う場合が多いので、自己流の姓名判断は間違った結果をもたらすかもしれません。
部首の画数にも違いがある
また、姓名判断における特有の考え方から、ヘン・ツクリ・カンムリなどの部首と言われる部分は、一般の漢和辞典と画数が違う場合があります。
これは上述のように文字本来の意味を強く意識しているためです。
詳しくは、下記を参照してください。
漢和辞典には部首の説明があり、この考え方が正しいものであると判断されています。
数の漢字はその数が画数
なお、数を意味する漢字一から十は画数ではなく、呼数を適用します。
例えば、「四」は通常5画と数えますが、姓名判断では4画で数えます(昔は棒4本で表していた為)「八」についても同様に8画で数えます。
二と七が同じ2画で同じ意味となっては具合が悪いですよね。
々は同一文字の繰り返し
また、佐々木の「々」は同一文字の繰り返しと考え「佐佐木」と直して字画を計算します。
より正確な鑑定の為には、漢字については漢和辞典で事前に調べられる事をお薦め致します。